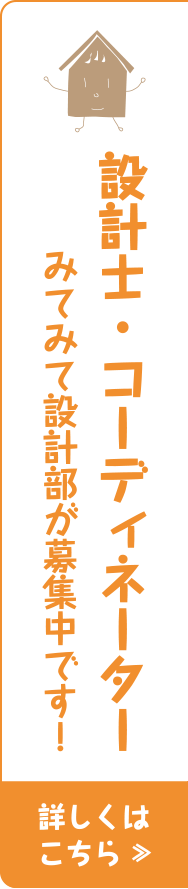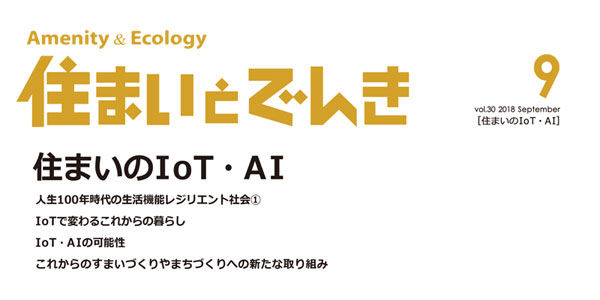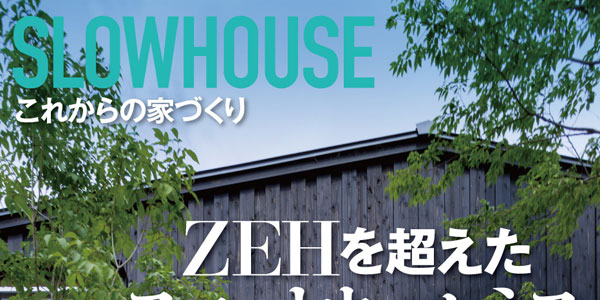こんにちは、気づけばすっかり冬の足音が聞こえてきましたね。皆さまぬくぬくお過ごしでしょうか?ぽえぽえくまです。
最近はインフルエンザが流行り始めて、学級閉鎖なんて話もチラホラ。手洗い・うがい・消毒、そして何より「しっかり寝る!」が大事です。夜更かし厳禁ですよ!
それにしても、この寒暖差。自律神経がジェットコースター状態で、めまいを感じる方も多いとか。さらに、急な冷え込みで筋肉がカチコチになり、ぎっくり腰になる方も続出中。
実は私も、季節の変わり目には数年に一度、腰が「ピキッ」と主張してきます。あれ、ほんとに油断大敵です…。夏に冷たいものばかり摂っていたツケが、今になって体の芯にズシンと響いてきます。だからこそ、今こそ「温活」!あったかいものを食べて、飲んで、血流をぐるぐる巡らせましょう。実は、寒いと体が体温を上げようと頑張るので、代謝が上がってダイエットにはうってつけの季節なんです。
こたつでぬくぬくも魅力的ですが、たまには立ち上がってストレッチや軽い運動をして、冬に負けない体づくりをしていきましょう!
家を守る、命を守る──耐震化という未来への投資
最近、あちこちで地震が頻発していますね。「またか…」なんて思っているうちに、いつか本当に大きな災害がやってくるかもしれません。でも、皆さんはその“いつか”に備えて、何か対策していますか?防災と一口に言っても、できることはたくさんあります。でも、いざ災害が起きたとき、私たちは本当に“動ける”のでしょうか?
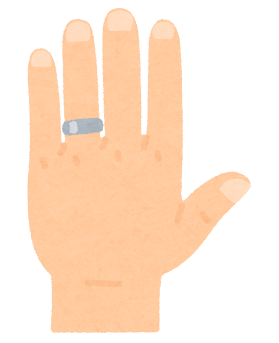
皆さんは「正常性バイアス」という言葉、ご存じですか?
これは、非常事態に直面しても「自分は大丈夫」「まだ大丈夫」と思い込んでしまう、ちょっと厄介な心理のクセ。この思い込みが、避難の遅れを招き、命に関わるリスクを高めてしまうことがあるのです。
東海地震が「来るぞ」と言われ始めたのは1970年代。きっかけは、1944年の昭和東南海地震で、駿河湾〜遠州灘の一部が“地震の空白域”として残ったことでした。南海トラフ沿いでは、過去1000年以上にわたり、マグニチュード8クラスの巨大地震が繰り返し発生しています。しかも、東海・東南海・南海の3つの領域が連動、または時間差で揺れることが多く、その周期はおよそ100〜150年。昭和南海地震(1946年)から、すでに約80年。「そろそろ来るかも…」と、1990年代には騒がれましたが、地震は起きず。低周波地震やスロースリップなどの“前兆っぽい”現象は観測されても、決定打はなし。地震予知の難しさが浮き彫りになり、2017年以降は「南海トラフ地震」として、広域的な防災体制が整えられました。
私が生まれる前から「30年以内に東海地震が来る」と言われていたのに、30年以上経った今も「30年以内に来る」と言われ続けているこの現実。
その間に、阪神・淡路、東日本、熊本、能登と、次々に大地震が起きました。「次こそ南海トラフか…?」と不安になるのも無理はありません。これだけ長く言われ続けていると、いざ本当に巨大地震が来たとき、「またか」と思って逃げ遅れる人が出るんじゃないか…そんな嫌な予感がしてしまいます。
2012〜2014年度に被害想定が公表され、2025年度には新たな想定も出ました。でも、10年経った今も、耐震化はあまり進んでいないのが現実。「本当に危機感、あるのかな?」と、つい首をかしげてしまいます。
そんな中、私は「これはいかん」と思い、防災士の資格を取ることを決意。防災士講座を受講し、そこで聞いた話がとても印象的でした。
「世界の陸地面積における日本の国土面積の割合は0.25%で国別61位。世界人口における日本の人口の割合は約2%で国別12位。では、2011年から2020年の間に世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、日本で発生した割合は?」
「答えは18%で、世界1位です。」
地震が多いのは今に始まったことではなく、日本はもともと“地震大国”。「なんでそんな場所に住んでるの?」と聞かれても、私たちにとっては“当たり前”だったんですよね。昔は「防災」なんて言葉もなく、災害対策は生活の一部でした。
でも今は、地盤の緩い土地に家が建ち、便利さと引き換えにリスクも増えました。「まあ大丈夫でしょ」「何かあっても国が何とかしてくれる」──そんな油断が、命取りになるかもしれません。
南海トラフ地震が起きたら、復興費用は国家予算を超えるとも言われています。広域で被災したとき、果たしてどれだけ迅速に支援が届くでしょうか?近隣の県も被災していたら、助けが来るまでに時間がかかるのは想像に難くありません。仮に一度目の揺れをなんとかやり過ごせたとしても、二度目・三度目の揺れに耐えられない家では、安心して暮らし続けることはできません。全壊した家を建て直すには、2000万円以上かかることも。
でも、その費用をすぐに用意できる人が、どれだけいるでしょうか?
今、耐震化しておけば、災害後も住み慣れた家で暮らせる可能性が高まります。
家具の転倒防止も大切です。能登の地震では、家具が倒れなかったことで助かった人もいました。ただし、それは「家が倒壊した中で、家具の隙間に逃げ込んで助かった」というケース。つまり、家そのものは倒れていたのです。
さらに、能登では今も関連死が増え続けています。これは何を意味しているのでしょうか?日本に住む限り、地震とは切っても切り離せません。家にいないとき、仕事中、外出中──そのとき地震が来たら、どこに逃げますか?津波の心配は?避難経路は?考えたこと、ありますか?
私は海が好きで、夫とよく海岸沿いをドライブします。そんなとき、夫は必ず「今、地震が来たらあそこに逃げる」と地形をチェック。四六時中考える必要はありませんが、時々「今、もし」と想像する癖をつけることが大切かもしれません。防災グッズを備えている方も多いと思います。でも、家が倒壊してしまえば、それらも使えなくなるかもしれません。南海トラフ地震では、這ってしか移動できない状況になる可能性もあります。一度目の揺れに耐えられても、すぐに二度目が来るかもしれません。
だからこそ、「すぐに逃げられる」「二度目にも耐えられる」家が必要なのです。「防災」と言いますが、もはや災害を完全に“防ぐ”ことはできません。
でも、「減災」はできます。家の耐震化も、その一つです。災害が起きる前に、「もし起きたらどうなるか」「その被害をどう減らすか」を考え、行動すること。それが、私たちの命を守り、未来を守る力になるのだと思います。
「うちの耐震って大丈夫かな?」「耐震化したいけど、何から始めれば…」そんな方は、ぜひみてみてまでご相談くださいね。
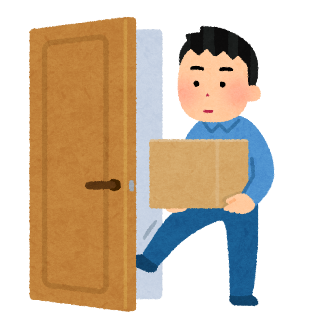
ぽえぽえくまでした。